◆1月7日(水)9:30 上野駅から
平日朝の通勤電車。横浜駅から上野東京ライン直通の東海道線に乗ったが、案の定というか、かなり混雑をしていた。
横浜駅はいつ行っても人の波が押し寄せてくるが、8番ホームの上にはスーツを来た人たちが大勢列を作っていた。数年ぶりに味わう東京の通勤ラッシュ。運よくドアのそばの安全圏に収まることができた。(といっても、押しつぶされそうなほどの人がいることには変わりないが。)
東京駅について、ほとんどの乗客が降りていったのが不幸中の幸いか。
羽沼は、軽く息をついて、立ったまま足元に置いたリュックサックを、車内の壁にもたれかかせる。
『羽沼さん。もう着いてたりしますか? 私、興奮しすぎちゃって、もう上野駅です! もし居たら会いましょ〜』
スマホが震えたと思ったら、彼女からそんなメッセージが来ていた。時刻は朝の9時半。羽沼は返す。
『すみません編集長。上野東京ラインに乗って、今東京駅を過ぎたあたりです。もう少しかかります』
すぐに返信が来る。
『そうだった! 羽沼さんが遠くに住んでいること忘れてました!』
『あれ、その理屈でいうと私が一番遠くに住んでますね???』
2連続でメッセージ。羽沼は、何か気の利いた返しをしようと思った。しかし、ちょうど車両アナウンスが鳴る。上野駅に着いたのだ。
「あ! 羽沼さん! こっちですこっち!」
上野駅のホーム。羽沼がたどり着くとそこにはベージュのコートを着たチアキが立っていた。彼女は羽沼を見つけると嬉しそうにぴょんぴょんと跳ね、こちらに手を振ってくる。羽沼はそれをどこか微笑ましく思い、笑みをこぼす。
シャッター音。チアキのスマホだ。
「へへ、マコト先輩に送っちゃお」
チアキは嬉しそうに微笑むと、羽沼が止める間もなくスマホを操作してマコトにその写真を送信する。
「きっとお昼頃にマコト先輩からリアクションがあるんじゃないかなって思いますよ!」
チアキはそう言って、小悪魔のような笑みを浮かべた。
「どうでしょうね、マコトは忙しいですから」
羽沼はそう言って笑い、駆け寄ってきたチアキに「ボストンバッグ、持ちますよ」と言う。
「そ、そんな。悪いですよ! 先輩のお兄さんにそんな」
「いえ、そこはあまり気にしないでください。ただでさえ宿泊先の手配などをしていただいていますし」
——今回の取材旅行の企画者は、元宮チアキその人だ。行き先は、群馬県の山奥にある「万座温泉」。自家用車で行くことのできる温泉地の中では最高峰であり、標高は1800メートルもある山の中だ。
かねてから、「週刊万魔殿」に旅行の枠を作りたいと言っていたチアキだが、どのような心境の変化があったのか、「旅行の中でも特に温泉が良い」と言い始めた。
言い始めた、というより、Teamsで(割と一方的に)そう宣言をしたのだ。
チアキの衝動的な一面には慣れていたつもりだったが——というより、これまでにも「取材命令」が飛んでくることはままあったが——今回の「命令」はいつもと少し様子が異なっていた。
(今回の旅行先に特段、取り立てて珍しいものは無し。祭りやイベントならともかく)
そう、タブレットPCの前で羽沼は考え込んだものである。
とはいえ、羽沼に文句などない。元より、取材旅行は好きだ。自分のもう一つの仕事である講師業にも活かせる。中学生たちにとっては、やはり紙の地図より活きた現地の写真である。
ちょうど群馬県といえば、嬬恋村にキャベツの栽培など、羽沼の担当領域である中学社会にドンピシャな場所だった。万座まで行けば、雪も積もっているだろう。中央高地の気候を示す資料としても価値が高いかもしれない。
それに、他ならぬ羽沼マコト(いもうと)の大事な後輩の頼みでもあり、羽沼家の生活を支える貴重な収入にもつながる話だ。
ホームの前方で、これから乗る特急列車を写真に収めているチアキを見ながら、羽沼はそう考えていた。
※チアキ撮影の、特急「草津・四万」

◆特急にて
——特急に乗り込む。比較的多くの人がいた。
特急「草津・四万」は首都圏と、吾妻線沿線の温泉地を結ぶ特急列車だ。上野駅を出て、終点の長野原草津口駅まではおよそ2時間35分で到着する。
長野原草津口駅は、その名が示すように「草津温泉」の入り口である。また、その道中、吾妻線の沿線には、伊香保温泉や四万温泉などといった名湯が並ぶ。
さすがは群馬県ですね、とTeams会議でチアキは楽しそうに言っていた。
——ドアが閉まり、静かに電車が動き出す。
平日昼間の車内は、グループで乗っている60代から70代の旅客が多かった。それと、外国人の観光客も。通路側に座っている羽沼の右斜め前には、スーツを着た青年の姿もあった。彼は黒い大きなリュックを膝の上に置いて、一人で静かに本を読んでいる。
「あれ、そういえば羽沼さんって荷物少ないですよね」
不意に質問。羽沼は答える。
「2泊3日ですからね」
羽沼は自分の足元の灰色のリュックサックを見る。標準的なサイズ。通勤カバンとしてみれば大きいサイズだろうか。
「ええっ」
しかし、羽沼の思考に反してチアキは驚きの声をあげる。そして、
「そんな……むしろ2泊もするんだったら……」と言いかけ、くるりと眼球がまわる。(あくまで暗喩だ。)
「やっぱり、それだけ旅慣れているということでしょうか!」
「はは、そうかもしれません。もっとも、衣類は圧縮をかけていますし、他にはタブレットPCだけあれば十分ですからね。自分用の写真は、スマホで撮りますから」
チアキは、「なるほど……」とポケットサイズのメモ帳を取り出して、何かをサッと書きつける。メモだ。
羽沼がチアキと直接会うのはこれが3度目だったが、彼女は何か新しいことを見聞きすると、すぐにメモ帳に書きつける。使っているメモ帳はどこにでも売っている——ああ、それこそ今使っているのはセブンイレブンで売っている黒いリングのメモ帳だ。
羽沼はそんな彼女を横目に見ながら、買っておいた黒豆茶をひと口。
(ああ、本の1冊でも持ってくればよかった。仕事とはいえ、他ならぬ編集長の隣で、他の雑誌の記事を書くのも少々気まずいな。)
ふと、そんな思考がぷかぷか。その時、羽沼の顔を覗き込む瞳。
「——作業はしなくても大丈夫ですか? 私のことは別に気にしなくても……」
まるで、宙に浮かぶソレを読んだかのように、チアキは問いかける。羽沼は少し驚きながら、返す。
「何か、顔に出てましたか?」
「……?」可愛らしく小首を傾げる。
「そうではないですよ。単に、私ならパソコンを開いて作業をするか、貴重な睡眠を取るか、そのどっちかだと思いましたから」
羽沼は、彼女がどこか眠そうな目をしていると気がついた。
「編集長、もしかして……また寝てないんですか」
チアキは、「あっ」と言う顔をした。
(わかりやすいな)そう思った。チアキは慌てて口を開く。
「ちゃ、ちゃんと寝ましたよ? 3時間くらい……」
羽沼は、自分でもわかるほどに苦い顔をした。
「流石に、寝ましょう。移動中まで気を張る必要はないですし、それに、温泉で寝落ちしたら大変ですから」
そう、諭した。21歳の若さがあるとはいえ、だ。
「はい……」しゅんとする。そして彼女は、ヘッドレストに頭を預け、動き続ける窓の外に目を向ける。
羽沼は少し、心がチクリとした。だから、少し、ほんの少しだけ遠慮がちに付け加えた。
「その……水をさすつもりはないですからね。ただ、睡眠不足は本当に……良くないですから」
チアキはその言葉に表情を明るくすると、
「大丈夫です、わかってますよ!」
と言って、目をつむった。
それを見届けて、羽沼はタブレットPCを開く。そして、フォルダの中から書きかけの原稿を引っ張り出す。編集長の許可も得たことだ、遠慮なく書こう。そう思って、羽沼は文字の海に沈む。
——しばらくそうしていた。すると隣から、コツン、と固いものがガラスに当たる音がした。目線だけ向ける。静かな寝息。音は、彼女の側頭部から生える角が、窓ガラスに当たった時の音だった。
——吾妻線に入り、特急は山を登る。重たい鋼鉄の塊が、確かな推進力と共に、山を登る。
羽沼は労働の成果を一時保存すると、山中を走る列車の感覚に目を向ける。静かで、近代的な山登り。
日頃は海のそばを高速で走る電車にばかり乗っているから、確かな足取りで分け入っていくこの列車は、どこか新鮮に思えた。
ふと、斜め前の青年に目を向ける。彼も、車窓を見ていた。
「んにゃ……」
真横から、眠たげな声。チアキだ。チアキが目を覚ました。
「羽沼さん……そろそろ、着きますかね」
彼女は窓ガラスと座席の落ち着くところに頭を収めたまま、そう尋ねてきた。声は眠たげで、尋ねるなりに二度寝しそうな様相だ。
「ええ、そろそろですよ」
羽沼はそう返し、座席のテーブルを畳んだ。
◆12:20 長野原草津口駅
「んー!」
チアキが勢いよく伸びをする。ポキポキと、彼女の背筋から音が鳴る。羽沼もそれをみて、軽く腰を回す。背骨の関節が鳴る音。最近抱えている、微かな腰の痛みも、温泉に入れば良くなるだろうか。そんなことを考えた。
羽沼たちが降り立ったのは、長野原草津口駅のホーム。今日はよく晴れていて、比較的暖かい冬の日。
観光客たちは皆、特急を降りて、そのまま出口の方へと向かっていった。
(そうか、ほとんどの乗客が、草津温泉の方に行くのか)などと、羽沼は思う。
「よし! 頭もスッキリしました! 今から深呼吸をします」
チアキはそんなことを言い、冬の冷気を肺におさめていく。どこか、神妙な顔をしていた。
そして、三度深呼吸をすると、満足したのか笑顔でバッグを持つ。そして、対面の路線に止まっている電車へと視線をやる。
「私たちは、次はあれに乗るんですね」
——万座・鹿沢口行の普通列車。車両の扉は閉じられたまま、始発を待機している。
「あ、押して開けるタイプですね」
チアキは、たったと走って扉を開ける。羽沼も電車に乗り込む。
車両内には、青いジャージを着た学生たちが数人座りながら話をしていた。それくらいだ。ガラガラのローカル線。チアキは「よいしょ」と言いながら席に着く。羽沼はその対面に座る。
チアキは少しだけきょろきょろと車内を観察するように視線を巡らせると、最後に羽沼と目を合わせて、「いえーい」と小さくピースする。
「だいぶはしゃいでますね」羽沼はそう言った。チアキは返す。
「もちろんです! だって、移動は旅の大事な要素じゃないですか。もっとも、誌面には載らない箇所ですけど」
誌面に載らない、と発音する時、チアキはほんの少しだけ唇を尖らせるような表情をした。だが、すぐに得意げな、そんな表情も浮かべた。そして、言う。
「たとえ記事にはならないとしても、頭には……それこそ、記憶として残りますからね」
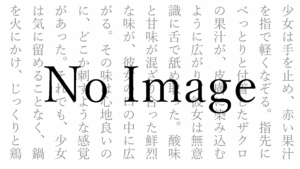
コメント